| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.07.23|経営・マネジメント
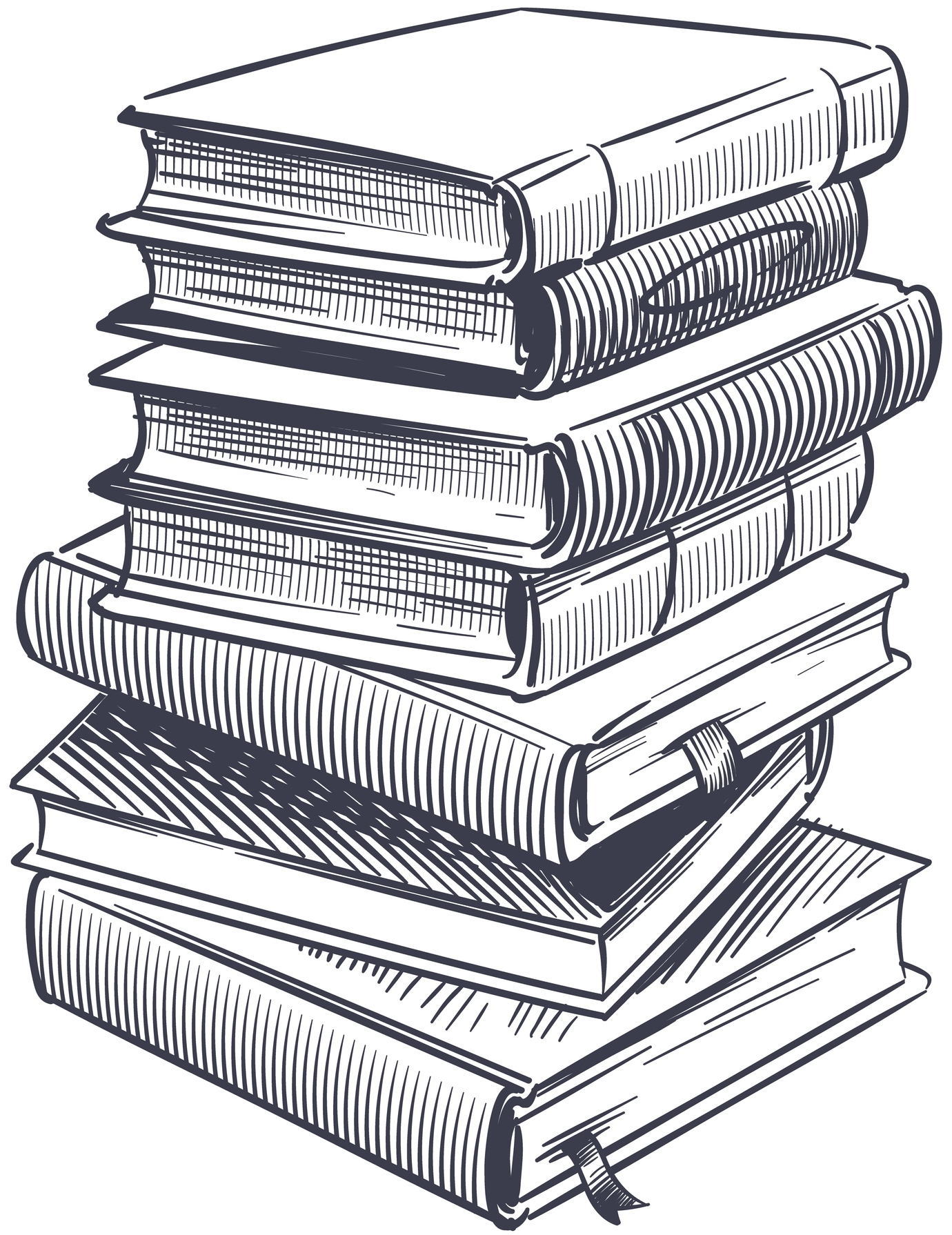
恐れのない組織
「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
著者:エイミー・C・エドモンドソン(著)、村瀬俊朗(解説)、野津智子(翻訳)
出版社:英治出版
発売日:2021年2月3日
著者について
昨今、組織における“心理的安全性”の重要度が増してきている。心理的安全性とは「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」のことだ。
職場環境の心理的安全性が高い場合、ミスが起こった場合に迅速に報告され、すぐさま修正が行われる。さらに、グループや部署を越えた団結が可能となり、イノベーションにつながるかもしれない斬新なアイデアが共有されるようになる。つまり、複雑かつ絶えず変化する環境で活動する組織において、心理的安全性は価値創造の源として絶対に欠かせないものなのである。
そして本書は、心理的安全性を“職場の個性”ではなく、リーダーが意図的に築かなければならない「職場の特徴」と位置づける。そして、心理的安全性を創出・強化することは、組織のあらゆる階層でリーダーが負うべき責務だと説く。本書を通じてリーダーは、心理的安全性の高い組織がもたらすメリットと、その実現するためのプロセスを具体的に学ぶことができるだろう。

“We have a low level of shame." - Sid Sijbrandij
(私たちは“恥の感度”が低い。 - シッツェ・シブランディ)
この言葉は、GitLabの共同創業者であるシッツェ・シブランディ氏のものです。GitLab とは「DevOps プラットフォーム」と呼ばれる、効率的なソフトウェア開発と運用を一気通貫で支援するサービスです。開発者やエンジニア以外の方には耳慣れないかもしれませんが、現在は世界中の数万社以上が開発現場で GitLab を採用しており、そのユーザーコミュニティは急速に拡大しています。
そんなGitLabですが、一般的な企業の常識を大きく超えるほど透明性と分散型の文化を徹底し、ユニークな組織運営を行っていることで知られています。特に注目すべきは、世界67か国以上に在籍する2,000名超の従業員を抱えながら、完全リモート(オールリモート)体制を貫いている点です。国籍も文化も異なる多様なメンバーが、オフィスも決まった就業時間も持たずに協働し、プロダクトを作り上げています。
GitLabはこうしたオールリモート体制のまま、法人化からわずか7年後の2021年にNASDAQに上場。時価総額64億ドル規模のユニコーン企業へと成長しました。なぜ、これほど大胆な働き方が可能なのでしょうか。その秘密は、シブランディ氏をはじめとする創業陣が、心理的安全性の高い「恐れのない組織」を徹底して築き上げてきたことにあると私は考えています。
本書によれば、心理的安全性とは「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」と定義されています。優れた製品やサービスを生み出すには誠実で正直な意見交換とフィードバックが不可欠ですが、率直に話すことには「相手に嫌われるかもしれない」という対人リスクが伴います。心理的安全性が高い組織では、このリスクを乗り越えて建設的な議論が行えます。
冒頭のシブランディ氏の言葉が示すとおり、GitLabは創業当初から心理的安全性の高い組織を目指してきました。「恥の感度が低い」とは、失敗を責めない文化が醸成されているということです。失敗が咎められないと分かっているからこそ、チームは自由に意見を交わし、イテレーション(反復による改善)を加速できます。
同社の失敗への向き合い方を象徴する出来事として、2017年1月31日に発生したGitLab.comのデータベース削除事故があります。この事故では約6時間分のユーザーデータが失われ、サービスも数時間停止しました。一般企業であれば不祥事を社内にとどめがちですが、GitLabは事故直後から徹底したオープン対応を行いました。
事故発生後、GitLabは障害状況を即座に公開し、SNSで復旧状況をリアルタイム発信しました。「データを喪失し申し訳ない。CEOとして心からお詫びする」とシブランディ氏自ら謝罪文を掲出し、原因や復旧策も隠さず共有しました。トップが失敗を認め責任を表明する姿勢は、社内外に誠実さを示すと同時に、社員にも「隠さず報告してよい」というメッセージとなりました。さらにエンジニアチームはデータ復旧の過程を外部に向けてライブ中継しています。
一方で、誤ったコマンドを実行したエンジニアは「team-member-1」と匿名化され、社外発表でも個人名は伏せられました。これは「透明性のために個人を犠牲にしない」という経営判断によるもので、シブランディ氏は「今後も事故対応で個人が特定されないようにする。透明性ゆえに誰かを晒し者にする意図はない」と明言しています。同時に「当人が受けるストレスを認識しており、チーム全体で支援する」と述べ、社員を守る姿勢を示しました。GitLabは重大事故時でも犯人探しをせず、組織全体の課題として受け止める文化を持っているのです。
VUCA時代において、企業はもはや「過去の成功」の延長線上では生き残れません。不確実性と変化が激しい現代では、環境の兆候をいち早く捉え、即座に適応する力が不可欠です。その前提となるのが、心理的安全性を組織文化として深く根付かせることです。
ただし心理的安全性は自然発生的に“ボトムアップ”で醸成されるものではありません。本書でも繰り返し述べられているように、心理的安全性はリーダーシップの意図的な働きかけによって生まれ、維持される職場の特性です。2017年の事故で示されたように、トップが失敗を率直に認め、当事者を守り、学びを組織全体に共有する行動がメンバーの安心感を決定づけます。リーダーの最も重要な仕事の一つは、誰もが最高の仕事をするために必要な文化をつくり、育て続けることではないでしょうか。
対人関係のリスクを取っても安全だと信じられる職場環境であること。それが心理的安全性だと、私は考えている。意義ある考えや疑間や懸念に関して率直に話しても大丈夫だと思える経験と言ってもいい。心理的安全性は、職場の仲間が互いに言頭・尊敬し合い、率直に話ができると(義務からだとしても)思える場合に存在するのである。(P.30)
感じよく振る舞うことは、心理的安全性と同意ではない。同様に、気楽さや心地よさを指すものでもない。対照的に、心理的安全性とは、さまざまな観点から学ぶために、建設的な対立を厭わず率直に発言することなのだ。(P.42)
詐欺と隠蔽は、返答として「ノー」も「無理です」も認めないトップダウンの文化でおのずと生まれる副産物である。(P.114)
実のところ、その創造的なプロセスは本質的に繰り返しの作業であり、面白い作品になるかどうかは、誠実で正直なフィードバックを得られるかどうかにかかっている。(P.148)
心理的安全性を生み出し強固にすることは、組織のあらゆるレベルのリーダーの責務である。(P.247)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル