| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.05.13|自己啓発
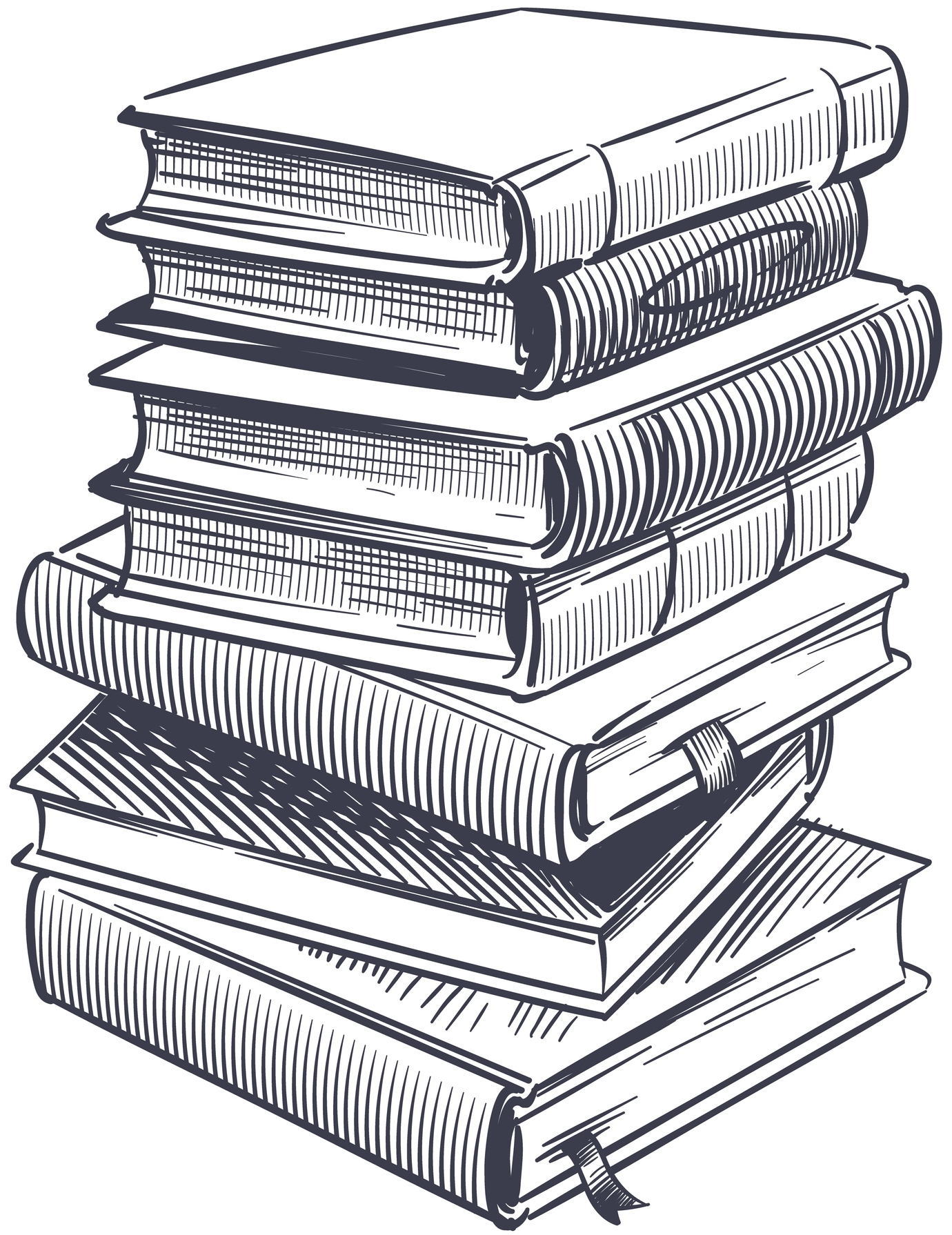
知覚力を磨く
絵画を観察するように世界を見る技法
著者:神田房枝
出版社:ダイヤモンド社
発売日:2020年10月21日
著者について
人は、最初に手にした情報にひっぱられやすい性質がある。情報が溢れる現代社会では、そのせいで判断を間違えることも少なくない。私たちが何を見て、どう感じるか。そして感じたことをどう受け止めるか。こうした土台になる「知覚」があって、初めて「考える」ことができるのだ。
ここで大切なのは、知的な仕事や問題解決の出発点が知覚だという点だ。どんな知覚を持つかで、そのあとに続く作業の質が大きく変わる。ビジネスの課題解決や新しいアイデアづくりはもちろん、日々のちょっとした判断や人生の大きな決断も、すべて知覚の力に左右されるのだ。
そして本書では、問題解決の出発点である「知覚力」をどう磨き、どうビジネスに活かしていけば良いのかを解説している。本書のテーマである「見えないものを観る力」こそ、独自性を育み、イノベーションを生み出す源泉となるだろう。

“At Sony, we assume that all products of our competitors have basically the same technology, price, performance, and features. Design is the only thing that differentiates one product from another in the marketplace." - Norio Ohga
(ソニーでは、競合他社の製品は技術・価格・性能・機能は基本的に同じだと考えています。市場で製品を差別化できる唯一のものはデザインなのです - 大賀典雄)
これは、東京藝術大学で声楽を学んだ後、オペラ歌手・指揮者として活躍し、のちにソニー株式会社の社長・会長へと転身した異色の経営者・大賀典雄氏の言葉です。アメリカの作家ダニエル・ピンク氏の著書『A Whole New Mind』でも、この発言が引用されています。
大賀氏はCDプレーヤーの開発・普及に尽力したのをはじめ、その後もMD、CD-ROM、DVDといった光記録メディアの商品化を推進し、ソニーを総合エンターテインメント企業へと導いた人物として高く評価されています。こうした功績は、大賀氏が幼少期から培った音楽への深い造詣があったからこそ成し得たものでしょう。本書のテーマである「知覚力」、すなわち大賀氏が磨き上げた「見えないものを観る力」が、まさに新たな価値の創造を可能にしたのです。
そもそも大賀氏がソニー(当時は東京通信工業株式会社)と関わりを持つようになったきっかけは、東京藝大在学中に出会った一台のテープレコーダーだったといいます。試作段階のテープレコーダーを紹介された大賀氏は、その再生音に歪みが多いことに注目し、「音が歪みすぎている」と辛辣に指摘しました。そのうえで、改良点のリストと回路図をまとめてソニーに送りつけ、共同創業者である井深大氏・盛田昭夫氏に「生意気で面白い若者」と強烈な印象を与えたのです。やがて大賀氏はソニーの嘱託技師として迎え入れられ、昼は開発者・夜は声楽家という二足のわらじを履きながらキャリアを重ねました。そして、1964年には取締役になり、1982年にはついに社長に就任します。この時代、ソニーは「ウォークマン」をはじめ数々の大ヒット商品を生み出すことになります。
大賀氏が学生時代にテープレコーダーの“歪み”を見抜いたエピソードは、本書の「私たちは純粋によく見ることをしていない」というフレーズを想起させます。多くの人が「こんなものだろう」と見過ごしていたかもしれない再生音のわずかな違いを、大賀氏は「知覚」したのです。『イノベーターのジレンマ』で知られるハーバードビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授が「イノベーションはほとんどいつも周縁部から起こる」と述べているように、大賀氏は目の前の世界を「絵画を観るように」あるいは「オペラを聴くように」捉えていました。ブラインドスポットになりがちな“周縁部”まで見つめることで、イノベーションを引き起こせたのではないでしょうか。
また、大賀氏は音楽の細部にこだわるように、製品の見た目や操作性にも厳しい目を向けました。大賀氏の指示によって、ソニーのオーディオ製品の筐体色はシルバーからエレガントな黒へ変更され、ロゴデザインも一新されます。新製品の発売直前であっても、ボタンの形状が気に入らなければ設計し直すよう命じ、出荷を遅らせるほどの徹底ぶりだったといいます。こうした大賀氏のこだわりが、ソニー製品の使い勝手と高品質なブランドイメージを確立し、「製品を差別化できる唯一のものはデザイン」と言い切れるほどの競争優位性を築いていったのです。
絵画を観るように、オペラを聴くように、一つひとつの要素を丁寧に見つめ、そこに生まれるわずかな解釈のズレを大切にする。本書は、そうした「知覚する」という行為こそが私たちの思考をしなやかにし、企業の競争優位性を生み出すと強く訴えかけます。いまや急激な変化が日常となった時代だからこそ、大切なのは「まだ見ぬもの」を捉える視点を持つことなのかもしれません。
知覚の価値は、他人とは異なる意味づけそれ自体のなかにあります。専門家であろうと門外漢であろうと、知覚にはその人なりの独自性があります。他人と異なる解釈にはつねに創造性のポテンシャルが秘められており、これこそが知覚が持つ絶大な意義なのです。(P.35)
現状にすっかり満足しきって近視眼的になっていると、人間は新しいものに対してまず疑念を抱いてしまいます。 それがバイアスとなって、知覚すべきものをみすみす逃してしまうのです。(P.66)
高い創造性は「関連性がより希薄なものをあえて結びつけること」で実現されます。これが提唱されてから半世紀以上経たいまも、この説の正しさはあらゆるところで証明され続けていますから、慣れ親しんだ分野の外にも広く「学びのアンテナ」を張っておくことは意識すべきでしょう。(P.72)
つまり、私たちは「純粋によく見る」という行為をしていないのです。(P.100)
共感というのは、相手の身になって感じ、解釈することです。つまり、共感力とは、自分の知覚を超え出て、2人分の知覚を得る能力なのです。(P.244)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル