| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.09.24|自己啓発
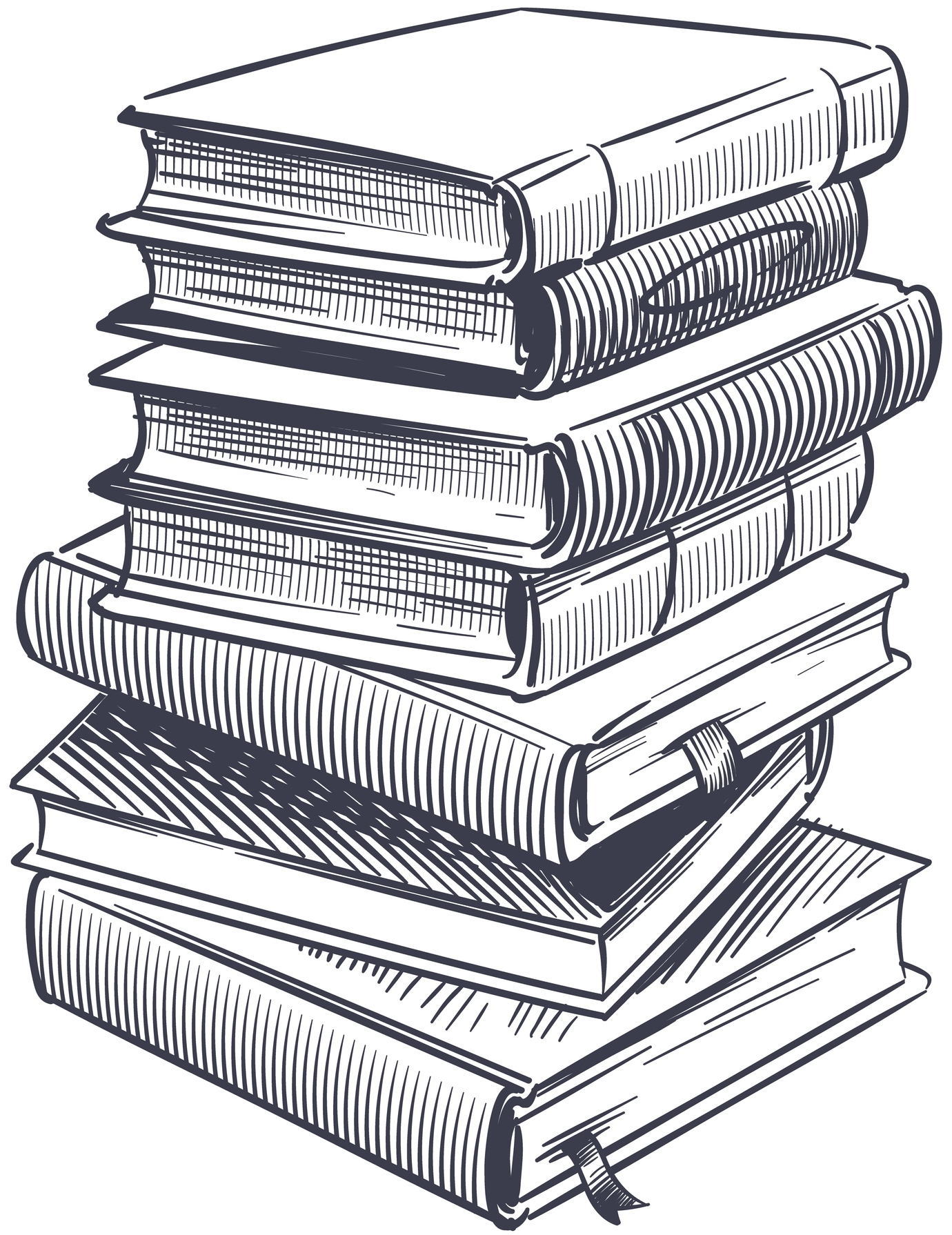
選択の科学
コロンビア大学ビジネススクール特別講義
著者:シーナ・アイエンガー(著)、櫻井祐子(翻訳)
出版社:文藝春秋
発売日:2014年7月10日
著者について
人生は自分ではコントロールできない変数に満ちている。どこで生まれ、どんな家庭で育つかは自分では選べない。両親がどんな信念を持ち、どんな教育を施すのかも同様だ。誰と出会い、どんな考えの人とどんな会話を交わすかも、完全には制御できない。
では、人間がコントロールできる“変数”とは何なのか。本書では、それが「選択」だと説く。私たちはどこに住み、何を学び、どんな生き方をするのかを選択できる。しかし、ここで重要なのは「選択肢が多ければ多いほど幸福」だと考えるのは幻想だということだ。選択は、自分自身の人生の主導権を持つという意味で不可欠である一方で、選択を他人に委ねることが幸福につながる場合もある。
本書では、人生のあらゆる場面で求められる「選択」について、心理学・経営学・哲学・生物学など多角的な視点で解説している。意思決定の質を高めたい経営者にとって、確かな指針となる一冊だ。

“The essence of strategy is choosing what not to do." - Michael E. Porter
(戦略の本質はやらないことを選ぶことにある - マイケル・E・ポーター)
経営学には「意思決定論」という分野があります。意思決定論は、目標達成のために複数の選択肢から最善を選ぶプロセスを扱う学問です。もし世界の変数が限られ、すべてを計算機上でシミュレーションできるなら、「最も合理的な決定」は数式で導けるでしょう。しかし現実はそう単純ではありません。『選択の科学』が示すように、私たちの選択は“知らず知らずのうちに”他者の行動や文化的文脈、フレーミング(提示のされ方)に影響されます。さらに、人間の認知にはヒューリスティックに由来するバイアス(認知の癖)があり、判断を体系的に歪めることがあります。したがって意思決定論は、単なる最適化ではなく、限定合理性のもとでいかに良質な選択を設計・実行するかを探る営みでもあります。
では、“良質な選択”とは何でしょうか。私たちはしばしば「短期は良いが長期は悪い」「将来のために今は我慢すべきだ」といった評価を行います。しかし“良質さ”は、置かれた環境・時代・文化という文脈で変動する、きわめて流動的な性質を持ちます。しかも世界のすべての変数を定義できない以上、「唯一の最適解」を論理的に確定することはできません。ゆえに、“良質かどうか”の判定以前に重要なのは、自分の心の状態を把握し、どのバイアスが働きやすいかをメタ認知することではないでしょうか。
冒頭の言葉は、ハーバード・ビジネス・スクール教授で競争戦略論の第一人者であるマイケル・E・ポーター氏のものです。ポーター氏は代表作『競争戦略論』で、競争におけるトレードオフの重要性を強調します。トレードオフとは、一方を採れば他方を捨てる関係のことで、戦略とはこのトレードオフを引き受け、意図的に「やらない」領域を定めることだと説きます。言い換えれば、資源は有限であり、「やらない」を明確にするときにはじめて「やる」が輪郭を持つのです。
もちろん、ポーター氏の論点は企業戦略だけでなく、私たちの人生の選択にもそのまま当てはまります。とりわけ人工知能の時代において、日々の些細な選択の累積が将来に及ぼす影響は、かつてよりも大きくなっていると感じます。
1970年、未来学者アルビン・トフラーは著書『未来の衝撃』で、情報過多が意思決定を困難にする「選択過剰(choice overload)」を予見しました。今日では、SNSや動画プラットフォームがアルゴリズムで私たちの関心を増幅し、小さなクリック(選択)がエコーチェンバーのように反響し続けます。まるでてこの原理のように、微細な選択が将来の環境をさらに自分好みに偏らせ、次の選択をも方向づけてしまう。つまり、私たちは“選択の結果”によって自分の“選択環境”そのものを作り替えているのです。ここまで来ると、もはや「何を選ぶか」だけでなく、どういう選び方を繰り返すと、どんな選択環境が将来に生成されるのかまで視野に入れなければなりません。
だからこそ、本書が提唱する「選択とは、自分や環境を自らの力で変える能力である」という見方が重要になります。人工知能は生き方を提案することはできても、決定することはできません。私たちは、この“増幅ループ”に呑み込まれず、むしろ望ましい方向へ自己増幅が働くように、「選び方」そのものを設計し直す必要があります。小さな選択は、小さな設計の見直しから変えられます。そうした反復が、未来の選択環境を少しずつ書き換えていくのです。一歩は小さくても、自己増幅の向きを自ら定められる限り、私たちはより良い未来へ軌道修正できるはずです。
わたしたちが「選択」と呼んでいるものは、自分自身や、自分の置かれた環境を、自分の力で変える能力のことだ。選択するためには、まず「自分の力で変えられる」という認識を持たなくてはならない。(P.29)
わたしたちには、選択の物語を生み出し、他者に伝える義務があると言っても過言ではない。というのも、このような物語は知ったが最後、けっして他者によって奪われることがないからだ。(P.50)
だれもがみな、正規分布曲線上で、一番居心地の良い場所を探そうとする。そこに到達するために真実を曲げなければならないのなら、それも仕方のないことだ。(P.140)
わたしたちが賢明な選択ができるかどうかは、自分の心の状態をどれだけよく知っているかに、少なからずかかっているようだ。もっと選択肢が欲しいというのは、こう言うのと同じことだ。「自分が何を欲しいかはわかっている。だから選択肢がどんなにたくさんあっても、自分の欲しいものを選ぶことができる」。(P.297)
実のところ、選択をまったくせずにすむ方法など存在しないのだ。「選ぶべきか、選ばざるべきか」という問いにどう答えようと、選択を行うのがあなただということに変わりはない。でも選択を行うからといって、必ずしも辛い思いをする必要はないのだ。(P.371)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル