| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.12.01|自己啓発
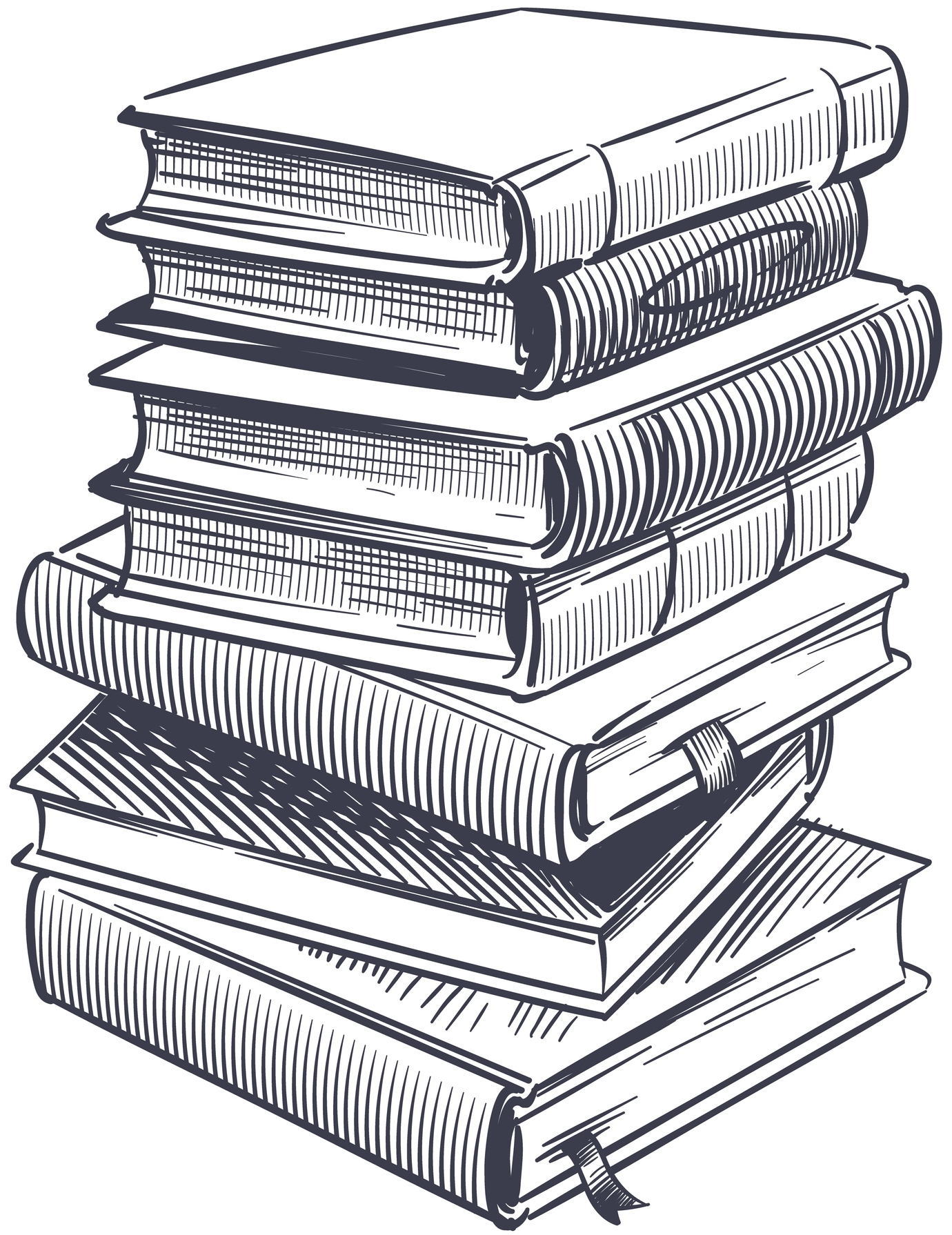
SAME AS EVER
この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方:人の「行動原理」が未来を決める
著者:モーガン・ハウセル(著)、伊藤みさと(翻訳)
出版社:三笠書房
発売日:2024年11月21日
著者について
私たちは常に予測不能で変化の激しい時代を生きている。生成AIの進化、世界情勢、金利とインフレの急反転など、先行きはなお不透明だ。2015年の時点で誰もが2025年の生成AIの爆発的普及を予測できなかったように、きっと私たちは2035年の未来を正確に予測することは不可能だろう。
しかし、「10年後に何が変わるか」よりも「10年後も変わらないものは何か」を考える方が、実は重要だというのが本書の主張だ。ウォーレン・バフェットは、景気が悪かったとき友人に「1962年のベストセラーのチョコバーは何だか?」と尋ね、「スニッカーズだ」と答えたうえで、“いつの時代でも普遍なもの”に投資を行い、長期的な成果を上げてきた。
本書は「移り変わる世界の中で決して変わらないもの」に焦点を当て、歴史や個人のエピソードを通じて変わらない教訓を浮き彫りにし、それを将来に活かす方法を探る。読むことで、変化に振り回されない判断軸と、不確実性に備える思考が身につくだろう。

『天災は忘れた頃にやって来る』
この言葉は、明治後期から昭和初期に活躍した物理学者・寺田寅彦氏が遺した言葉です。大災害は頻繁に起こらないがゆえに、人々の記憶から薄れた頃に不意に襲ってくる。本書で紹介されている金融理論家ハイマン・ミンスキーの「安定は不安定を育む」という逆説の通り、長く平穏な状態が続くと人々は警戒心を失い、かえって次の混乱の種を撒いてしまいます。寺田氏は、防災科学を説くときにこの言葉をよく口にしていたと言われています。
寺田氏はまた、人間が災害を適切に恐れ、備えることの難しさも洞察しました。1935年に浅間山小噴火を視察した際、下山してきた学生が「あんなの大したことはない」と呑気に語るのを聞き、駅員が「いや、そうではない」と首を振った様子を目撃した寺田は、「ものを怖がらな過ぎたり、怖がり過ぎたりするのはやさしいが、正当に怖がることはなかなか難しい」と述べています。すなわち、人は油断(過小評価)と過度の恐怖(過大評価)の両極に陥りやすく、リスクを「正しく恐れる」ことこそが難しいと喝破したのです。
寺田氏の時代から約100年が経った今、私たちはリスクを正しく評価し、正しく恐れることができているのでしょうか。決して、それが実践できている方は多くないと思います。著者のモーガン・ハウセルが本書で指摘するのは、まさにこの「人間の性質は変わらない」という点です。時代がどれだけ進み、テクノロジーが進化しようとも、人間が必要以上にリスクを恐れ、あるいは慢心に陥りやすいという、人間の本質的なOS(オペレーティング・システム)は、古代よりずっと変わっていません。
2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏は、人間の行動の本質として「プロスペクト理論」を説きました。これは、人は不確実な状況下で意思決定を行う際、利益よりも損失をより大きく感じ、合理的な判断ができないことがあるという行動経済学の理論です。つまり、寺田氏の言葉に照らし合わせれば、人は往々にしてものを怖がりすぎてしまうのです。
しかし、人間はただ“怖がり”なだけかというと、そうではありません。1973年、米国の社会学者B・F・マクラッキー氏は災害に関する報告書の中で、人々が目の前に危険が迫るまでその危険を認めない傾向があることを指摘しました。これを「正常性バイアス」と呼びます。寺田氏が浅間山小噴火を視察した際に出会った、下山してきた学生のように、リスクを正しく恐れることが極めて難しいことを示しています。
災害だけではなく、同じことは経営でもいえます。経営者は、目先の好況や一時的な成功に酔うことなく、滅多に起こらないが一度起これば致命傷となるリスクを想像し、あらかじめ備えておかなければなりません。楽観的な成長シナリオだけで計画を立てれば、外部環境の急変や「想定外」のトラブルに直撃されたとき、一気に事業継続が危うくなるからです。本書に通底するのは、そうした人間のバイアスを前提にしたうえで、あえて慎重さと余裕を組み込んだ意思決定を行おうというメッセージだと感じました。
もちろん、時代の流れを読み、トレンドの最前線を追っておくことは大切です。江戸時代前期の俳諧師・松尾芭蕉は俳諧の理念として「不易流行」を説きました。不易とはいつまでも変わらない本質のこと。そして流行とは時代に応じて変化することです。不易と流行を同じ位置に置くからこそ、確かな基盤に基づいた新しい芸術が生まれると芭蕉は説いたのです。芭蕉は代表作「奥の細道」の中でも「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず(変わらないものを理解しないで基礎は成立しないが、変わるものを理解しないときには進展がない)」と述べました。
目まぐるしく変わりゆく時代の中で「変化するもの」を取り入れていくことは大切です。しかしそれは、変わらない「不易」が基礎としてあってこそだと思います。本書で繰り返し語られる「いつの時代も変わらない人間の性質」を見つめ直すことは、まさにその不易を掘り当てる作業にほかなりません。読み終えた今、目先の変化やノイズに振り回されるのではなく、「10年後も変わらないもの」から逆算して選択する習慣を、あらためて身につけたいと強く感じました。
アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスは、「今後十年で変わるものは何か」と、しばしば尋ねられるそうだ。「『今後十年で変わらないものは何か』と質問されることはほとんどない」と彼は言う。「だが、こちらの質問のほうが実は重要なのだ」と。「決して変わることのないもの」が重要なのは、それを知ることで未来がどう形作られるか、確信が持てるからだ。(P.9)
「リスクとは、あらゆる可能性を想定し尽くしたと思ったあとに残っているものだ」これこそ、リスクの真の定義だ。想像しうる限りのリスクに備えたあとに残っているもの。リスクとは、あなたには予想できないもののことなのだ。(P.38)
たいてい、人は、物質的な財産を守るために、あらゆる予防策を講じる。その一方で、もっとはるかに大事なものを蔑ろにしている。なぜなら、それらには値札がついていないからだ。お金を払って手に入れるものではないがために、目が見えること、人との結びつき、自由といったものの真の価値がわからないのだ。(P.60)
悲観主義者のように貯蓄し、楽観主義者のように投資する。悲観主義者のように計画し、楽観主義者のように夢を抱く。(P.187)
自分が出世するために理不尽や厄介事をどのくらい我慢すればよいかを見きわめるスキルは過小評価されがちだが、きわめて重要なスキルだ。(P.208)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル