| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.01.23|経営・マネジメント
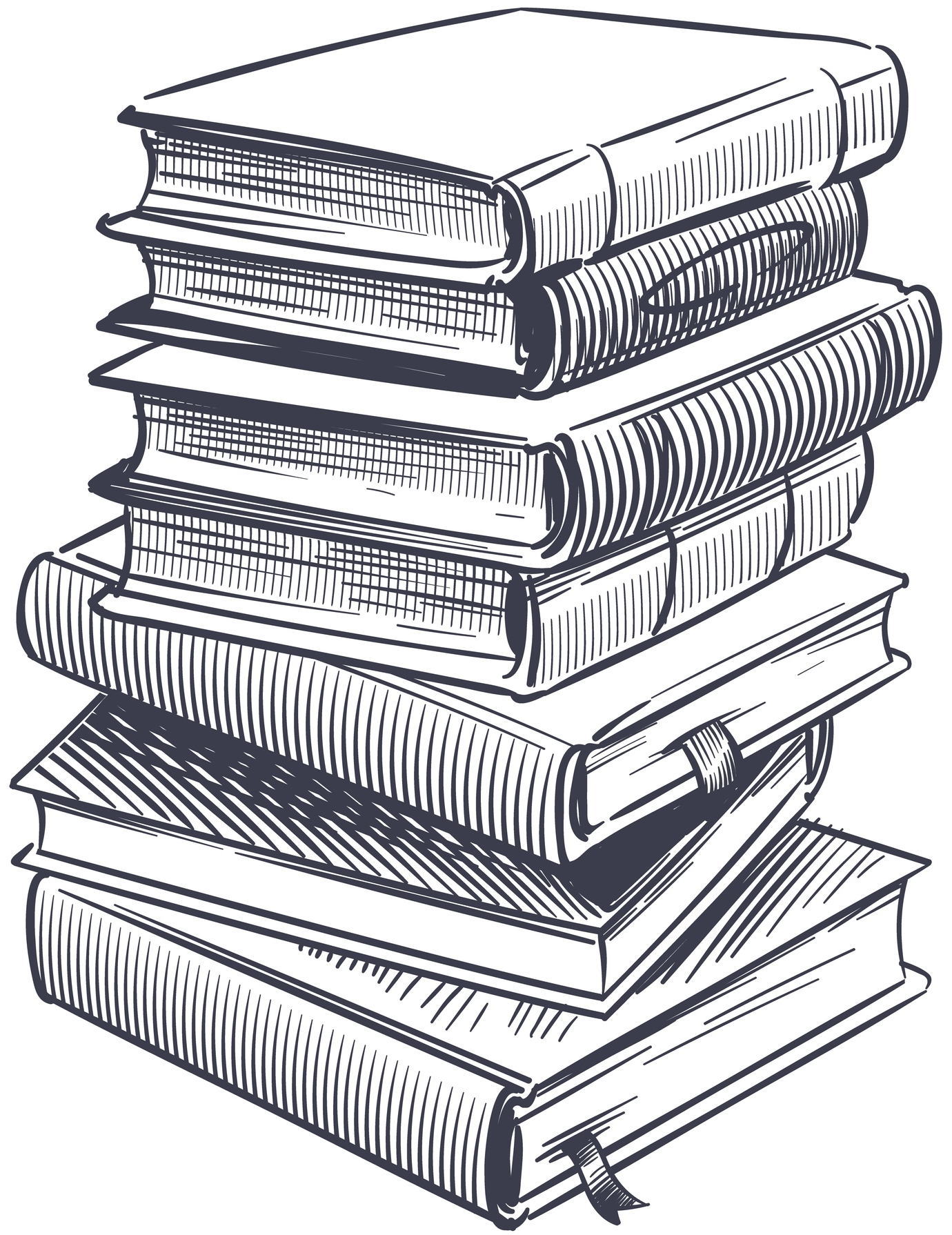
シン・ロジカルシンキング
著者:望月 安迪
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
発売日:2024年7月19日
著者について
私たちは子どものときから“正しい答えにたどり着くためには論理的思考が必要”だと学んできた。しかし生成AI時代の現代に、その理論は通用するのだろうか。なぜなら、論理的思考を突き詰めた先にあるのは、誰もが同じような結論にたどり着いてしまうという「思考の同質化」であるからだ。論理的に考えれば誰もが同じ結論に至るのであれば、そこに差別化の余地はない。
そこで著者が提案するのが「QADIサイクル」という新しい考え方だ。これは
Q:問い(Question)
A:仮説(Abduction)
D:示唆(Deduction)
I:結論(Induction)
という4つのステップを組み合わせたもの。まるでパズルを解くように、自分なりの視点で物事を考えていくための方法だ。
問いを立て、大胆な仮説を生み、その含意を論理的に導き、そこから新たな発見を見出す。本書が提唱する「シン・ロジカルシンキング」は、これまでのロジカルシンキングがもたらす「コモディティ思考の罠」を抜け出す方法を解説している。従来のロジカルシンキングに行き詰まりを感じている方にご一読いただきたい一冊だ。

“Aristotle founded or discovered logic by observing the world. ChatGPT thinks logically. Why? Because it notices all the logic in the data in its training set." - Stephen Wolfram
(アリストテレスは世界を観察することで論理学を確立・発見した。ChatGPTは論理的に考える。なぜか?それは、トレーニングセットのデータに含まれるすべての論理に気づくからだ - スティーブン・ウルフラム)
2024年10月、ChatGPTを展開するOpenAI社は新モデル「o1」を発表しました。o1モデルの特徴は、これまで生成AIが不得意とされていた論理的処理の精度が格段に上がったこと。o1では従来モデルのようにユーザーの入力に対して即答せず「考える時間」を設けることで思考プロセスを洗練させたといいます。国際数学オリンピック(IMO)の予備試験のスコアは、前モデル「4o」が13%の正答率だったのに対し、o1は83%の正答率を誇りました。
冒頭の言葉は、イギリスの理論物理学者で米ウルフラム・アルファの創業者であるスティーブン・ウルフラムの言葉です。アリストテレスを含め、私たち人間には“時間”という制約があります。そのため、観察できる“世界”のデータセットは有限です。一方でAIには時間の制約はなく、理論上は無数のデータセットの中から正しい論理を導けます。一世代前には、人工知能の性能が人類の知能を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)は2045年にやってくると予測する科学者もいました。しかし、驚異的な進化を遂げる生成AIのシンギュラリティは、ロジカルシンキングという一点に絞ればもっと早い時期にやってくるのではないかとも感じています。
人類は古来から、知的な営みにおいて「正解」や「真理」を見つける方法論を模索してきました。そしてアリストテレスが論理学を定式化して以降、“正しさ”の追求は人類の思考をリードしてきたともいえます。しかし、現代の生成AI時代においては、これが「思考の均質化」を助長しているようにも見えます。あらゆる情報がデータ化され、誰もが「正しい結論」へ効率よくたどり着けるなら、そこに“差異”や“独自性”はどのように生まれるのでしょうか。
ここでヒントになるのが、20世紀を代表する美術史家エルンスト・ゴンブリッチの考え方です。彼は代表作『芸術と幻影(Art and Illusion)』において、人間がどのように世界を“見る”のか、そしてアーティストがどのように“描く”のかを、心理学的視点から解明しようと試みました。そして、ゴンブリッチが言う「幻影(Illusion)」とは、鑑賞者が“リアルだ”と感じる視覚的な錯覚のことを指しています。真に客観的に見れば、そもそも絵とはそのものは平面上の絵具の塗り分けにすぎません。しかし私たちは、そこに三次元的な空間や質感を感じ取ってしまいます。つまり絵画とは、見る人が自分の中にある視覚的・知覚的な処理によって「本物らしさ」を作り出す幻影装置とゴンブリッチは解釈しました。
ゴンブリッチが提示した「幻影」の概念は、本書の核であるアブダクション(仮説思考)という思考プロセスと共通する点があります。アブダクションとは「限られた手掛かりから大胆に仮説を立てる」発想法を指しますが、絵画の「幻影」が、鑑賞者自身の内面にある視覚スキーマや知覚プロセスによって補完される点は、まさに「問い」を投げかけ、それに対する「仮説」を想像力豊かに作り上げるアブダクションに通じると感じました。私たちは実際には見えていないはずの奥行きや物体の質感を、頭の中で“一気に仮説”として組み立て、まるで本物のように感じ取る。これは論理的に整合性を検証する前の段階で、まず“こうかもしれない”という推測を素早く立てるアブダクションの特徴と似ています。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、写実的な絵画が主流を占める中、ピカソはあえて“遠近法”や“単一視点”という常識を崩し、多視点から捉えた形態を一つの画面に統合するキュビズムを生み出しました。これは、見えるものをそのまま描写するのではなく、“本来見えていないもの”を作品に織り込むという大胆な実験でした。リアリズムを当然と考えていた世の中に対して、「もし人間の顔を、横顔と正面を同時に描いたらどうなるか?」という問いを立てたうえで、仮説を具体的な形に落とし込んだのがキュビズムだと言えます。
この「リアルに見えないものをあえて描いてみる」「多視点を強引に統合する」といった発想は、まさにアブダクションが生み出す“飛躍的な仮説”の代表例ではないでしょうか。論理の筋道に沿って順々に導き出すのではなく、まず突飛な問いを設定し、“かもしれない”という仮説を可能な限り解き放ち、そこから新しい形式や解釈を試みる。このプロセスこそが、ピカソのような芸術家が起こしたイノベーションの核心にあるように思えます。
ビジネスの世界でも、優れた仮説を生み出す力は重要です。Uberは「タクシー」という既存の概念を解体し、「個人の遊休資産の活用」という新しい文脈に置き換えました。これもまた、ピカソのキュビスムのように、既存の枠組みを創造的に組み替えるアブダクションと言えるでしょう。『シン・ロジカルシンキング』が目指すのは、まさにこのような大胆な仮説を生み出す思考法なのではないでしょうか。
プロセスが変わらなければアウトプットは変わらない(P.4)
僕らがここから読み取らなければならないのは、知的生産とは「与えられたもの」から「与えられていないもの」を導くゲームであるという本質だ。(P.42)
再現性は必要でありながら、差別化もつくり出さなければならない──その同時達成を可能にするための考え方が、本書が伝える思考の型だ。(P.78)
「So what?」だけでは足りない、そこに偏ってはいけない。僕らはそこに意外性を重ねた「So what’s new?」をこそ問わなければならない。(P.130)
楠木建先生は著書『ストーリーとしての競争戦略』で、「賢者の盲点」という考えを伝えている。「それだけ見ると一見して非合理なのだけれども、ストーリー全体の文脈では合理性を持つ」というものだ。(P.228)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル