| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.03.13|経営・マネジメント
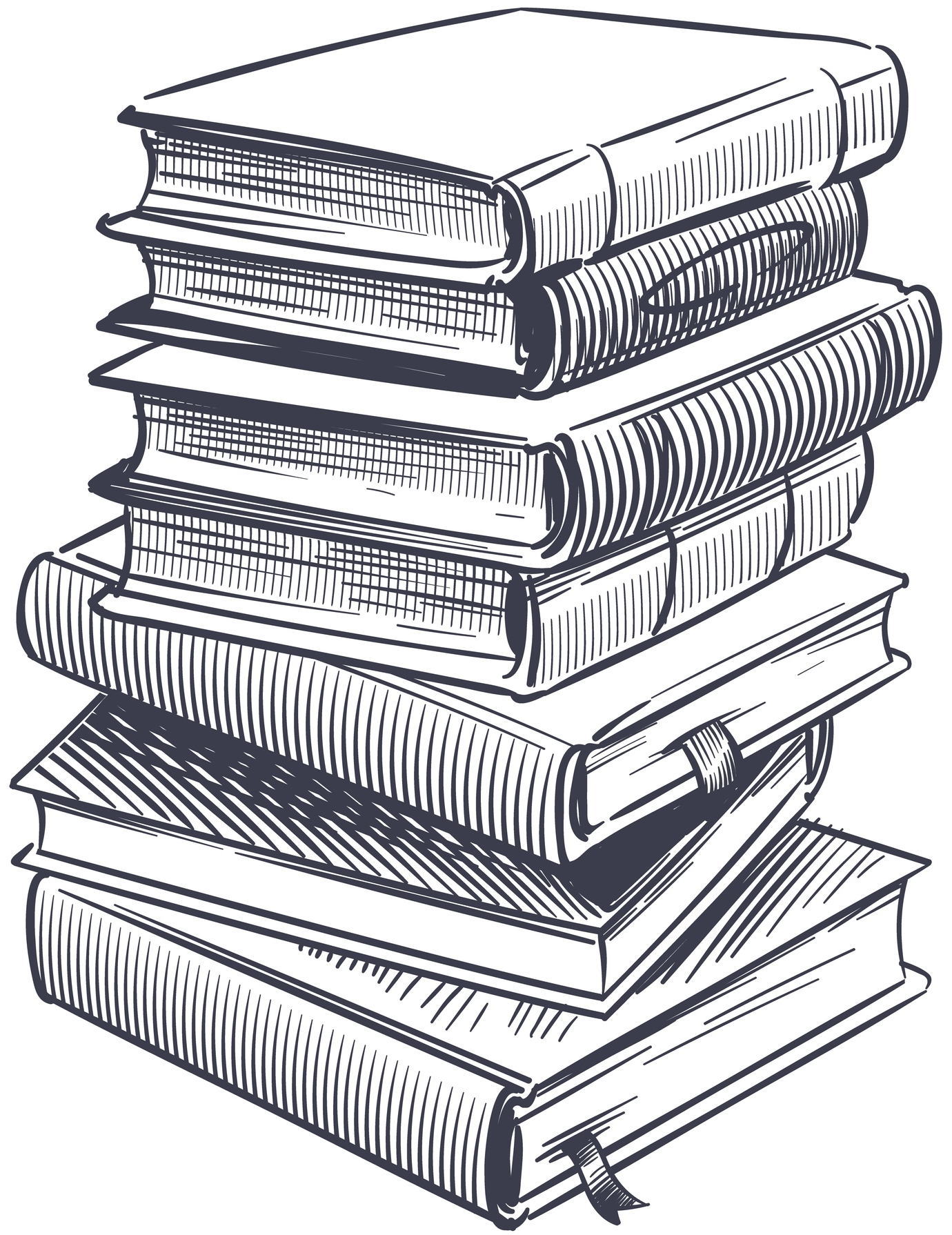
両利きの経営
「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く
著者:チャールズ・A・オライリー(著)、マイケル・L・タッシュマン(著)、入山章栄(監修)、冨山和彦(解説)、渡部典子(翻訳)
出版社:東洋経済新報社
発売日:2022年6月24日
著者について
チャールズ・A・オライリー(Charles A. O'Reilly III)。スタンフォード大学経営大学院教授。カリフォルニア大学バークレー校で情報システム学の修士号、組織行動論の博士号を取得。同校教授、ハーバード・ビジネススクールやコロンビア・ビジネススクールの客員教授などを経て現職。専門はリーダーシップ、組織文化、人事マネジメント、イノベーションなど。スタンフォード大学のティーチングアワードやアカデミー・オブ・マネジメント生涯功労賞などを受賞。また、ボストンのコンサルティング会社、チェンジロジックの共同創業者であり、欧米やアジアの幅広い企業向けにコンサルティング活動やマネジメント研修(破壊に対応するための企業変革や組織刷新、リーダーシップなどのプログラム)に従事してきた。スタンフォード大学のSEP(エグゼクティブ・プログラム)でも教鞭を執る。
マイケル・L・タッシュマン(Michael L. Tushman)。ハーバード・ビジネススクール教授。コーネル大学で科学修士号、マサチューセッツ工科大学(MIT)で組織行動論の博士号を取得。コロンビア大学教授、MIT客員教授、フランスINSEAD教授などを経て現職。専門は技術経営、リーダーシップ、組織変革など。アカデミー・オブ・マネジメント特別功労賞や全米人材開発機構(ASTD)生涯功労賞などを受賞。また、ボストンのコンサルティング会社、チェンジロジックの共同創業者であり、コンサルティング活動やマネジメント研修に従事。ハーバード・ビジネススクールのAMP(アドバンスト・マネジメント・プログラム)、マネジメント育成・変革リーダーシップ・組織刷新プログラムのファカルティ・ディレクターも務める。
一世を風靡した大企業が、競争力を失ってしまうのはなぜか。通常、企業は既存の自社サービスの質を深掘りし、よりよいサービスに磨き込んでいく。この「知の深化」の活動によって、企業は安定して質の高い製品・サービスを提供したり、社会的な信用を得て収益化を果たすことができる。
しかし本書では、成功した企業ほど「知の深化」に偏って最終的にイノベーションが起こらなくなると警鐘を鳴らす。これは“サクセストラップ(成功の罠)”と呼ばれ、過去の成功を再現すること一辺倒になってしまうのだ。収益を上げているうちは企業は存続できるが、ひとたび大きな環境変化に見舞われると、過去の成功が再現できなくなり、やがて衰退する可能性がある。知の深化のみに傾倒した企業は短期的な成功に留まり、長期的に競争力を保ち続けられなくなるのだ。
そこで本書が提唱するのは、「知の深化」と「知の探索」を両立させる“両利きの経営”だ。知の探索とは、自身の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げていく活動を指す。両利きを実践できている企業は、安定した基盤を保ちながら変化への対応力も備えているため、長期的な成長が可能になる。不確実性の高い現代社会においては、「知の深化」による効率性と「知の探索」による革新性のバランスを取ることこそが、企業の持続的な競争力の源泉となるのだ。

“It turns out, to disrupt someone else’s business, you have to add a net new line of business to your own portfolio." - Geoffrey Moore
(要するに、他社のビジネスを破壊するには、自社の事業ポートフォリオにまったく新しい事業を1つ追加しなければならないということです。 - ジェフリー・ムーア)
2025年3月5日、ディスカウントストア大手のトライアルホールディングスが西友を3,826億円で買収することを発表しました。同時に注目されたのが、小売企業ではなく“IT企業”としてのトライアルの強みです。同社はトライアルの38店舗にAIカメラを2326台導入し、商品の陳列状態を監視するシステムを構築しています。さらには、レジに並ばず決済できるセルフレジカートも独自開発しており、顧客の購買行動分析を行うことで陳列の最適化やレイアウトの更新を行なっています。2024年6月期には24期連続の増収を達成、そして営業利益率2.7%という小売業界の中では高水準の利益率を維持しています。
トライアルホールディングスの好業績の背景には、既存の事業で収益を上げる「知の深化」だけでなく、新事業を開拓する「知の探索」を怠らない“両利きの経営”を続けた結果であると私は考えています。1984年に産声を上げたトライアルは、もともとPOSシステムの開発やコンピューターの受託製作を主力事業としてきました。そこから8年後の1992年にトライアル1号店を開業。2000年代には、高度経済成長期に栄えた総合スーパー(GMS)業態が次々と撤退する中、トライアルはGMS居抜に次々と出店を繰り返し、急成長を続けました。
そして2018年には、主力事業である既存の小売事業を維持しながら、IoT・AIといった新技術事業を開発・実装するためにグループ内に新技術開発専属の組織「Retail AI(リテールAI)」を新設。AIカメラやセルフレジカートなど、流通小売業界に特化したAIソリューション事業を展開してきました。
トライアルの歩みは「既存の小売事業の強化」と「新規のテクノロジー事業への挑戦」を有機的に結びつけながら成長してきた点に大きな特徴があります。ディスカウントストアとしてGMS居抜で急成長を遂げつつ、IT企業としての側面を活かし、Retail AIという新技術事業を主軸に加える。その姿は、まさにムーアの言う“ビジネスを破壊するには新しい事業を自社ポートフォリオに取り込む必要がある”という言葉を体現しているように感じます。
振り返ってみると、小売業界の勝ちパターンは、多くの場合「徹底したコスト削減とスケールメリットの追求」によって形成されてきました。ところが、デジタル技術が当たり前となり、店舗運営においてもビッグデータやAIが実用レベルにまで落とし込まれ始めた今、勝ちパターンの方程式は様変わりしています。こうした変化が当たり前になった社会において、「両利きの経営」を実行する企業とそうでない企業との間には、これからいっそう大きな差が生まれるのではないでしょうか。
しかし同時に、忘れてはならないことは「恐竜はユニコーンを打ち負かすことができるし、ユニコーンはすぐに恐竜になりうる」ということです。過去の強みや成功パターンに安住するだけでは、瞬く間に“恐竜”化するリスクがある一方、新興の“ユニコーン”も油断すればすぐに時代遅れとなる。二兎を追い、二兎を捕まえても、そこで努力を止めたらすぐに兎は逃げていきます。大切なのは、「知の深化」と「知の探索」を両立させる“両利きの経営”を継続していくこと。つまり、どれだけ成功しても“二兎を追い続けること”が何よりも大切ではないかと感じました。
企業活動における両利きは、主に「探索(exploration)」と「深化(exploitation)」という活動が、バランスよく高い次元で取れていることを指す(P.10)
各社はダイナミック・ケイパビリティ、すなわち「企業が急速に変化する環境に対応するために、内外のコンピテンシーを統合、構築、再構成する能力」をうまく活用することができた。その結果、成熟事業(既存の強みを有効活用できる分野)と新領域(新しいことをするために既存の資源を使う分野)の両方で競争可能となっている。中核市場と技術を変えたから、失敗を免れ、変化し適応することができたのだ。(P.58)
強い文化を持つ組織は通常、期待される行動を非常にはっきりと伝える。万人向きの組織ではなく、おそらく特別な人だけが成功することを打ち出している場合もある(「少数精鋭、誇り高きマリーン」など)。こうしたメッセージは、文化の模範となるような態度や行動をとる従業員を鮮やかに感動的に表現したストーリーを通して、しつこく伝えられる。そういう人を持ち上げて、しばしばヒーローに仕立て上げるのだ。ストーリーはリーダー自身が語ることもあるが、リーダーに代わって、従業員や顧客などから文化的メッセージが広まっていく場合もある。(P.209)
スケーリングの黄金律は「学習する前に投資するな」である。(P.339)
読者の皆さんにぜひ考えていただきたいことがある。恐竜はユニコーンを打ち負かすことができるし、ユニコーンはすぐに恐竜になりうる。(P.468)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル