| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.04.07|経営・マネジメント
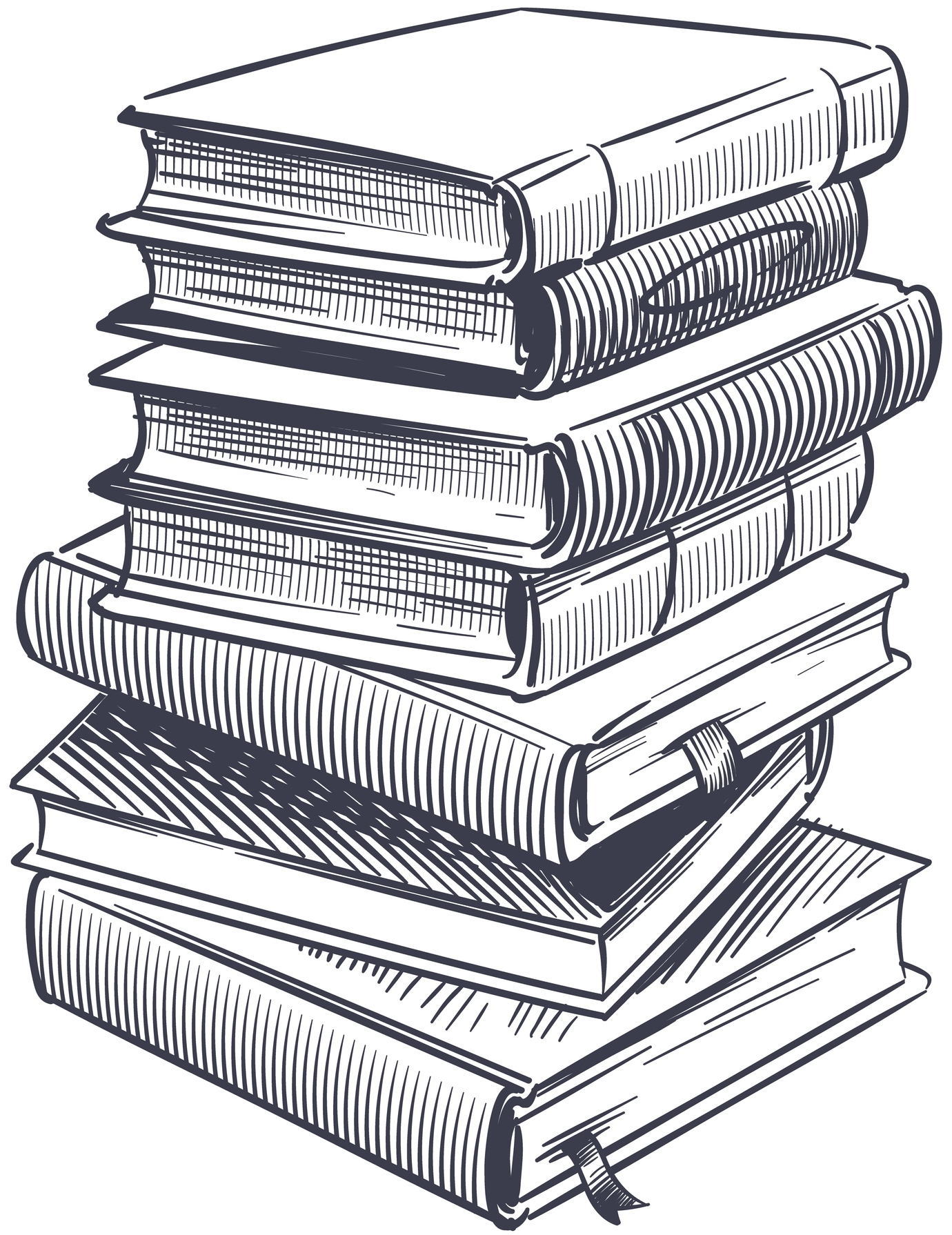
なぜ人と組織は変われないのか
ハーバード流 自己変革の理論と実践
著者:ロバート・キーガン(著)、リサ・ラスコウ・レイヒー(著)、池村千秋(翻訳)
出版社:英治出版
発売日:2013年10月24日
著者について
ロバート・キーガン(Robert Kegan)。ハーバード大学教育学大学院教授(成人学習・職業発達論)。30年あまりの研究・執筆活動を通じて、人が成人以降も心理面で成長し続けることは可能であり、現代社会のニーズにこたえるためにもそれが不可欠であるという認識を広めてきた。授与された名誉学位や賞は多数。高く評価された著書The Evolving SelfとIn Over Our Heads(ともにHarvard University Press)は、多くの言語に翻訳されている。
リサ・ラスコウ・レイヒー(Lisa Laskow Lahey)。ハーバード大学教育学大学院「変革リーダーシップ・グループ」研究責任者。共著にChange Leadershipがある。専門は発達心理学。教育者としての経験も長く、大人の意味体系の評価法として世界中で用いられている発達診断法を開発した研究チームのリーダーも務めた。チームが個人の成長を後押しし、同時に個人がチームを適切に機能させるために貢献できるようにする方法論をテーマに、執筆と実務をおこなっている。
本心から「変わりたい」と思っていても、それを実際の行動に移せる人は極めて少ない。近年の研究によると、医師から「生活習慣を改めないと心臓病で死にますよ」と言われた患者のうち、85%が自身の生活習慣を改められなかったという。これは、決して本人が「怠惰である」わけでもないし、「生きたい」と本気で思っていないわけでもない。自分を変えられないのは、人が変化によって失われるものを守ろうとする「裏の目標」を無意識に抱えており、二つの相反する目標の両方を本気で達成したいからなのだ。
本書では、この意識の上では変化を望んでいるにもかかわらず、無意識のレベルでその変化を阻止しようとする心理的な働きのことを「変革をはばむ免疫機能」と呼んでいる。そして、免疫機能がどのように作用し、目標達成を阻害しているのかを明らかにする「免疫マップ」を作成し、変化を起こせない“本当の問題”をあぶり出す方法を解説している。
個人や組織で「目標」を設定しても、なかなか達成できないと感じている方に、ぜひご一読いただきたい一冊だ。

“I want everyone inside of Microsoft to take that responsibility. This is not about top-line growth. This is not about bottom-line growth. This is about us individually having a growth mindset." - Satya Nadella
(マイクロソフト内の全員がその責任を持つことを望みます。これは単なる売上成長の話ではありません。利益の成長の話でもありません。これは私たち一人ひとりが「成長マインドセット」を持つことについてなのです。 - サティア・ナデラ)
2014年2月、ナデラ氏がマイクロソフト社のCEOに就任した時、同社は“もはやイノベーションを起こせない企業”というイメージが強まりつつありました。AppleのiOSやGoogleのAndroidがモバイルアプリを軸にした新しいエコシステムで世界を席巻する中、マイクロソフト社が発売したWindows Phoneはシェアで大きな遅れをとっていました。
当時のマイクロソフト社の世間の印象は、いわば“PC時代の王者”。WindowsやOfficeをはじめとする製品群を自前で構築し、「ソフトウェアパッケージを売り切る」収益構造で時代を席巻していました。しかし、2007年のiPhoneの登場以降、ITの中心が「スマホ+クラウド」へ移行しつつある中で、マイクロソフトは従来のライセンス収益がドル箱であり続けるため、大胆なビジネスモデル変革に踏み切れずにいました。投資家のピーターティール氏は、マイクロソフトがWindowsやOfficeで“囲い込む”ビジネスを長年続けてきたことに対し、「テクノロジーイノベーションを阻害している企業」と厳しく評したこともありました。
もちろん、マイクロソフト社は決して「危機感を持っていなかった」わけではありません。当時からマイクロソフト社はクラウドサービスのAzureや、サブスクリプション型で提供されるOffice 365の展開、さらにはWindows Phoneの普及を進めており、「スマホ+クラウド」の時流に即したサービスを展開しようとしてきました。しかし、クラウドはAmazonのAWS、OSはiOSとAndroidがスタンダードとなる中で、マイクロソフト社は後発として他のビッグテックの背中を必死に追いかける状況。さらに、市場全体としてPC出荷台数が減少に転じる兆しが見え、主力事業であるライセンスモデルの限界を感じ始めます。
そんな中でCEOに就任したのが、インド出身のサティア・ナデラでした。ナデラは就任初日から「成長マインドセット」を掲げ、「大企業として守りに入るのではなく、リスクを取り、学び、挑戦し続ける姿勢を取り戻そう」と全社員に訴えました。つまり、真っ先に“社風改革”に着手し始めたのです。ナデラ氏はカロル・ドゥエック教授が提唱した“成長思考”の考え方をマイクロソフトに組み込み、「失敗してもいいから学びを生かす」風土を醸成しようと考えました。冒頭の言葉は、改革の中でのナデラ氏の発言だと言われています。
本書の「免疫マップ」に照らし合わせると、当時のマイクロソフト社には、「新たなビジネスモデルへの転換を本気で進めたい」という表向きの目標がある一方で、社内には「従来のWindowsやOfficeライセンスを捨てられない」という“裏の目標”が深く根づいていたように思えます。二つの相反する目標の両方を本気で達成したいから、マイクロソフト社の業績は低迷していたと言えるのではないでしょうか。表面的には「クラウドやモバイルへシフトしなければ」という危機感を抱いていても、“裏の目標”として「高収益を生み出すライセンスモデルを崩したくない」「既存ユーザーの強い要望を裏切れない」「失敗したら大事な評判を失うかもしれない」という思い込みがあるため、大胆な一歩を踏み出しきれない。ここに「変革をはばむ免疫機能」が働いていたと考えられます。
ナデラ氏はCEO就任後、真っ先に「成長マインドセット」を掲げ、“裏の目標”を心理的に少しずつ解体していきました。たとえば社内で失敗を責めない文化を作ろうと、ハッカソンの開催やエンジニアたちへの裁量権拡大などの仕組みを導入し、挑戦を奨励しました。これによって社員の「失敗して評価を落とすくらいなら現状を守ったほうがいい」という隠れた恐れをゆるめたのです。さらに、モバイル端末向けにもOfficeをオープンに展開したり、競合プラットフォーム上でのサービス提供を積極化したり、といった具体的施策を次々と打ち出しました。これは、「自社プラットフォームに閉じこもらないと、Windowsの価値や独占的優位が失われるのではないか」という長年の固定観念を事実上くつがえす行動と言えると私は感じました。
実際、本書でも強調されるように、競合するコミットメントを乗り越えるためには“実験”が欠かせないとされています。本書でいう“実験”とは、「もし自分たちの思い込み(たとえば“ライセンス収益を壊すと会社が傾く”)が間違いだったらどうなる?」という仮説を検証するために、小さな一歩でも実際に行動してみること。ナデラ氏の時代に始まった「クラウドファースト」「モバイルファースト」の取り組みは、まさにそうした行動実験を組織レベルで進める過程だったのだと思います。すると意外に「OfficeをiPadに提供しても、WindowsやOfficeへのブランド価値が下がるどころか、むしろ顧客接点が増えて新規ユーザーが広がる」という結果が見え始めた。そうして次々と固定観念を打ち砕く成功体験を積むうちに、マイクロソフト社全体の意識が変わり、やがてクラウド(Azure)やXbox、Surfaceシリーズ、GitHub買収、OpenAIとの連携などへと大胆に乗り出す下地が整っていったのです。
“裏の目標”に潜む強力な「固定観念」を検証するのは、決して容易ではありません。しかし、マイクロソフトほど巨大な企業でさえ、組織を「変えられた」のです。どんな人でも、どんな組織でも「変えられる」のだと私は信じています。そして、「人や組織はいつだって変われる」という“成長マインドセット”を周囲に共有し、学び続ける土壌を作ることこそが、経営者として最も重要な仕事の一つではないでしょうか。
本当の問題は、自分が本心からやりたいと望んでいることと実際に実行できることの間にある大きな溝だ。この溝を埋めることは、今日の最も重要な学習上の課題である。(P.12)
月並みなリーダーと傑出したリーダーは、どこが違うのか? それは、自分自身の、自分が率いるチームのメンバーの、そしてチーム全体の能力を高められるかどうかだ。(P.22)
変革がうまくいかないのは、本人がそれを本気で目指していないからではない。心臓を病んでいる人が禁煙の目標を貫けないとしても、その人は「生きたい」と本気で思っていないわけではないだろう。変革を実現できないのは、二つの相反する目標の両方を本気で達成したいからなのだ。(P.66)
くどいようだが、人間がいだく強力な固定観念のすべてが間違いだと決めつけるつもりはない。私たちが言いたいのは、その固定観念を表面に引っ張り出して検証しないかぎり、正しいか間違っているかを判断できないということだ。(P.382)
本当の変化と成長を促したければ、リーダー個人の姿勢と組織文化が発達志向である必要がある。ひとことで言えば、「大人でも知性を発達させられる」と期待しているというメッセージをメンバーに向けて発信すべきだ。(P.487)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル