| 制作費 | 49,800円 | (税込54,780円) |
|---|---|---|
| 維持管理費 | 月額4,480円 | (税込4,928円) |
|
まほろば文庫
LIBRARY
ビジネス書の書評ブログ |
LIBRARY |
2025.02.15|自己啓発
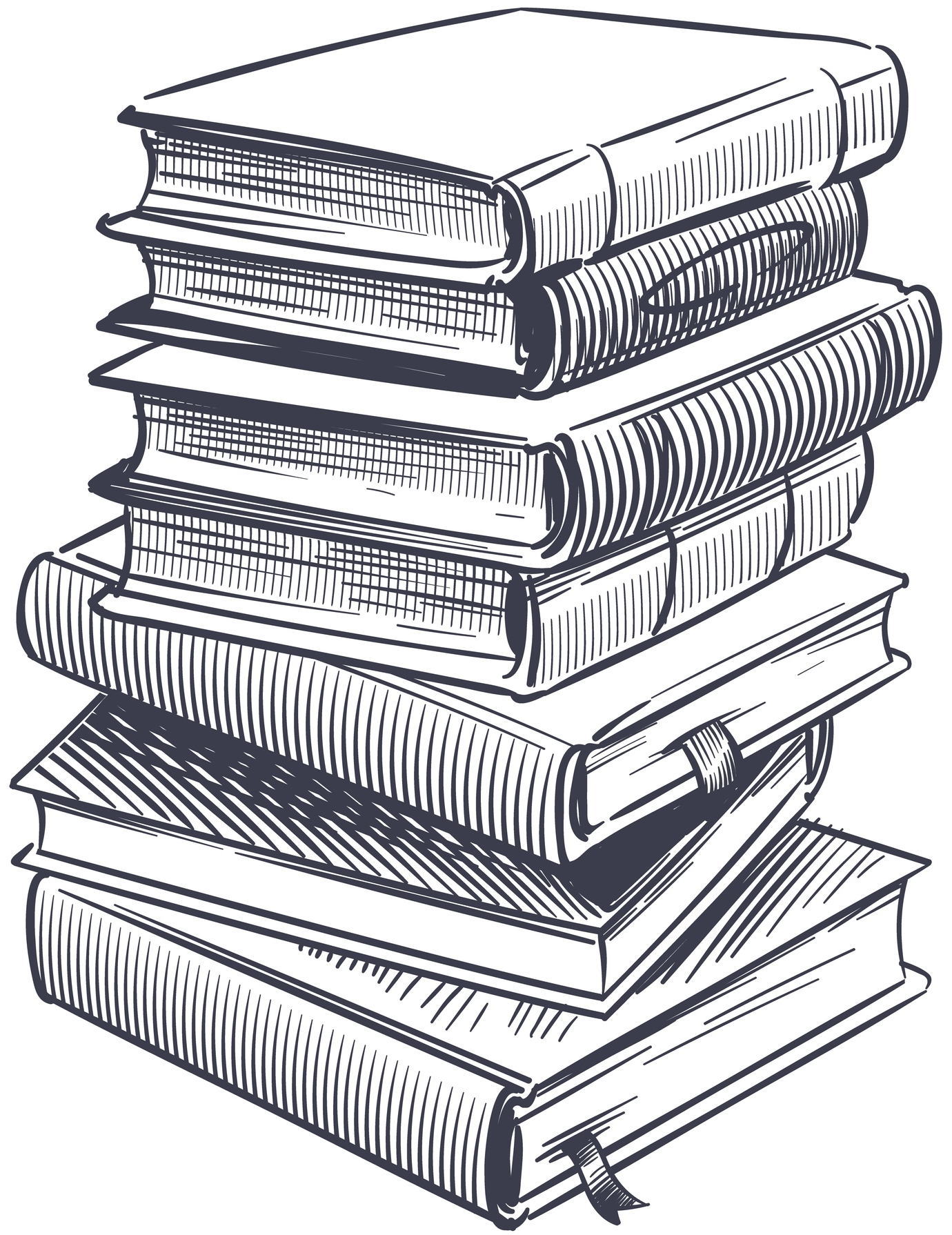
人生後半の戦略書
ハーバード大教授が教える人生とキャリアを再構築する方法
著者:アーサー・C・ブルックス(著)、木村千里 (翻訳)
出版社:SBクリエイティブ
発売日:2023年2月28日
著者について
「キャリアの頂点を極めた後、その先には何が待っているのだろう?」
仕事を続けるうちにふとこうした疑問が頭をよぎることはないだろうか。成功を追い求める中で燃え尽きそうになり、ふと気づけば家庭や健康まで後回し。それでも「もう少し頑張れば」と、いつまでも気合いを入れて走り続ける。
アーサー・C・ブルックスの『人生後半の戦略書』は、まさにそんな「仕事至上主義」から一歩離れ、中年以降をより幸福で有意義に生きるための方法論を提示してくれる一冊だ。著者自身はハーバード大学で幸福学を研究する教授であり、かつては大手シンクタンクのCEOとして忙殺される日々を送ってきた。そこで見えてきたのが、「成功依存症」は人生前半のエネルギーを倍増させる反面、人生後半には大きな空虚感や人間関係の摩耗をもたらすという“落とし穴”だった。
本書で提唱されているのは、そんな成功依存症から脱却し新たな人生を歩むための方法だ。人生後半の成功とは「自分のため」から「誰かのため」へと視点を移すこと。そんな、豊かな人生を送るために大切なことを教えてくれる一冊だ。

“It was a sign. I’m addicted to working… I’m basically killing myself by traveling so much, for no reason whatsoever." - Elton John
(あれは一つの兆候だった。私は仕事に依存している…理由もなくこんなに旅を重ねて自分を殺しているようなものだ - エルトン・ジョン)
音楽界で、史上最も成功したシンガーソングライターの一人であるエルトン・ジョン。1970年代以降、『YOUR SONG(君の歌は僕の歌)』をはじめ、彼の楽曲は出身地イギリスを中心に世界中で愛され、親しまれてきました。しかし、1970年代の彼は名声の絶頂にいながら、精神的にはどん底だったことはあまり知られていません。
1975年10月に行われたロサンゼルス・ドジャー・スタジアム公演。この公演はエルトンの名を世界中に轟かせ、名声を確固たるものにした記念すべき公演となりました。しかし、その直後にエルトンは自殺未遂を引き起こします。冒頭に記した言葉は、当時のインタビューでエルトンが発したものです。この出来事を機に一時活動停止を宣言し、実際1976年には燃え尽き症候群によって一度「引退」を表明しています。
2019年に公開された映画『ロケットマン』には、そんなエルトンの半生が描かれています。当時のエルトンは、成功へのプレッシャーや幼少期から抱えていた心の傷を紛らわすために、音楽制作や派手なパーティー、ドラッグに逃避する日々を送っていました。彼は文字通り仕事に没頭することで、現実問題から逃避し、それが常軌を逸した仕事依存につながったのではないでしょうか。
この記事の読者の方は、士業事務所・中小企業の経営者や勉強熱心なビジネスパーソンなど、社会的に成功した優秀な方が多いと思います。しかし同時に、どれだけ仕事で偉大な成功を収めたとしても、なぜか報われないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本書で著者は、「仕事依存」は一種の“快感への中毒”と捉え、脳内のドーパミン報酬系が関与していると説明しています。これは心理学で言う“オペラント条件づけ”にも通じる考え方で、成果を出せば周りから称賛される→さらに努力して成果を上げる→また称賛される……という正のフィードバックが習慣化されてしまうのです。こうした行動パターンはアルコールやドラッグの依存とも構造は同じで、抜け出すのは想像以上に難しいものです。
エルトンを始め、多くの「成功者」が成果をあげ続けた結果、不幸になるという例は枚挙に暇がありません。つまり再現性があり、認知心理学の分野でその理由について研究されるテーマなのです。本書が引用する研究によれば、人の「流動性知能」は20代〜30代でピークを迎え、その後は緩やかに低下します。一方で「結晶性知能」は高齢になっても伸び続ける傾向があります。
たとえば企業のトッププレイヤーだった人が、50代以降で“全体の指揮”や“経験の伝達”に回ることで再び輝くケースは珍しくありません。エルトンも、一連の出来事をめぐり、人生の主軸を“燃えるようなパフォーマンス中心”から“若手支援やチャリティー活動”にシフトしました。結果としてさらに大きな社会的影響力を発揮している姿は、まさに流動性知能→結晶性知能への移行を象徴しているように思えます。
「結晶性知能」へシフトするにあたって、本書で繰り返し述べられているのが「奉仕」というキーワードです。例えば本書では、紀元前1世紀に政治家・弁護士・学者・哲学者として活躍したマルクス・トゥッリウス・キロケが晩年に公開した『義務について』の次の言葉を引用しています。
「老人は(中略)肉体労働を減らし、頭を使う活動を増やすべきであるように思う。相談に乗ったり、実用的な知恵を教えたりして、友人や若者、そして何より国家にできるだけ奉仕するよう努力すべきだ」
これはキロケの経験則ではありますが、著者は奉仕を単に道徳的行為として扱っているわけではなく、科学的にも「幸福感を増幅させる行動特性」として捉えています。ハーバード大学が1938年から続けてきた Grant Studyでは、「良好な人間関係が長期的な健康と幸福を決定づける最大の要因」と報告されています。近代以降、脳科学や社会学の研究によって、その伝統的な知見が「科学的にも正しい」と立証されつつあるのが興味深いところではないでしょうか。
もちろん、本書は「成功」そのものを否定しているわけではありません。本書が問いかけているのは「あなたは、これまで築いてきた力をどう使いますか?」ということに尽きます。成功から奉仕へ。流動性知能から結晶性知能へ。各人が、自分の得意とする領域や環境を活かしながら“役割”を変えていく。そうすることで、人生後半はむしろ「新たな可能性」に満ちた時間に転換できると、著者は力強く説いているのです。
仕事を頑張る時期を超えた先にこそ、本当の人生が始まるということを本書は教えてくれます。才能や力をどう社会へ、そして次世代へつないでいくのか。そこに未来の幸福があるのです。仕事をバリバリこなしたい若い時期は、流動性知能をフル活用して幸福を得るのもよいかもしれません。しかし、もし今、あなたが「まだまだ成功を追いたい」と思いつつも、心のどこかに虚しさを抱えているなら、ぜひ本書を開いてみてください。自分の人生の脚本を変えるのは、決して遅すぎることはないのです。
「仕事の成功だっていずれ終わる」という事実から目をそらし、自分で自分の首を絞めているのです。(P.8)
キケロは歳を取ってからの生き方について3つの信念を抱いていました。第1に、ぐうたらせずに、奉仕に専念すべきであること。第2に、晩年に恵まれる最大の強みは知恵であり、学習と思考から生み出す世界観によって、他者を豊かにできること。第3に、晩年ならではの才能を活かす手段が相談を受けることであり、お金や権力や名声といった世俗的な見返りを狙わずに、他者を指導、助言、教育すべきこと。(P.52)
人生の後半は、知恵で他者に奉仕しましょう。あなたが最も重要だと思うことを分かち合いながら歳を重ねるのです。何かに秀でているということは、それだけで素晴らしいことなのだから、それ以上の見返りは不要です。そう思って生きていけば、歳を経るほど最高に秀でた存在になれるのです。(P.63)
成功に取りつかれた仕事依存症の人は、落ちこぼれたくないという恐怖にとらわれています。そのため、依存行動に振り回されている人全員に言えることですが、生活のなかに、友達や家族のために使える余裕を残しておきません。(P.152)
本書の読者の多くが減らすことになるのは、仕事です。このケースに当てはまる人で、仕事を減らしたくがないために恋愛関係や親子関係や本当の友情を再構築する気になれない人は、優先順位のバランスが崩れています。(P.165)

AUTHOR天野 勝規
株式会社まほろば 代表取締役
士業専門のホームページ制作会社「株式会社まほろば」の代表取締役。大阪教育大学 教育学部 卒業。総合小売業(東証プライム上場)、公益法人での勤務を経て29歳で起業。
独立開業時の集客・顧客開拓に関する相談から、年商数億円規模の事務所のマーケティング顧問まで幅広い対応実績。15年間で3,000事務所以上からご相談・お問合せ。
ホームページを活用しつつも、SEO対策だけに頼らない集客・顧客開拓の仕組みづくりを推奨している。
【保有資格】
社会保険労務士、年金アドバイザー2級
こちらの記事もどうぞ
書籍のジャンル